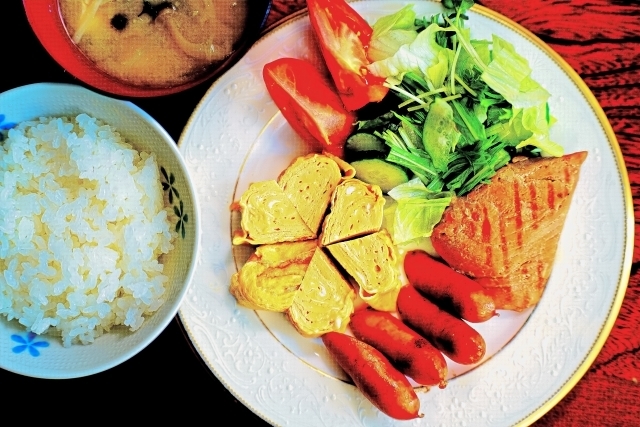こんにちは。
トレーナーの倉世古(くらせこ)です
今週は”ダイエット”の基本について書いていきたいと思います。
第一回目は”カロリー編”
体重の増減というのは摂取カロリーと消費カロリーのバランスで決まります。
摂取カロリーの方が多ければ太り。
消費カロリーの方が多ければ痩せます。
これがダイエットにおける原理原則です。
世の中には多くの”ダイエット法”があります。
有名なのは”糖質制限ダイエット”。
糖質さえ摂らなければ脂質やたんぱく質はどれだけ摂ってもよいというものです。
これにおいても結局はカロリーがオーバーすれば太ります。
ただ、脂質やたんぱく質で摂るカロリーよりも糖質をカットした分のマイナスカロリーの方が大きいから痩せているだけです。
体内の水分が抜ける事も体重減には大きく寄与しています。
他には”栄養価の高いものをたくさん食べて痩せる”というもの。
これもカロリーオーバーすれば太ります。
結局はカロリー収支です。
では、ダイエット時は摂取カロリーはどのくらいにすればよいのか。
当然、個人差はありますが、一つの基準だけお伝えします。
筋肉博士と言われている石井直方先生によると。
”除脂肪体重×30~35”
とされています。
”除脂肪体重”の求め方は、
「体重×(100-体脂肪率)÷100」
例えば、
体重60kgで体脂肪率25%の人の場合
「60×(100-25)÷100=45kg
除脂肪体重で45kg
これに30~35を掛けて可能摂取カロリー計算をすると。
1350~1575kcalとなります。
まずは、このように基準値を見つけていきます。
その後は、日々、体重の変化をチェックしながら摂取カロリーも調整してければよいでしょう。
今回は”ダイエット~カロリー編~”でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。